

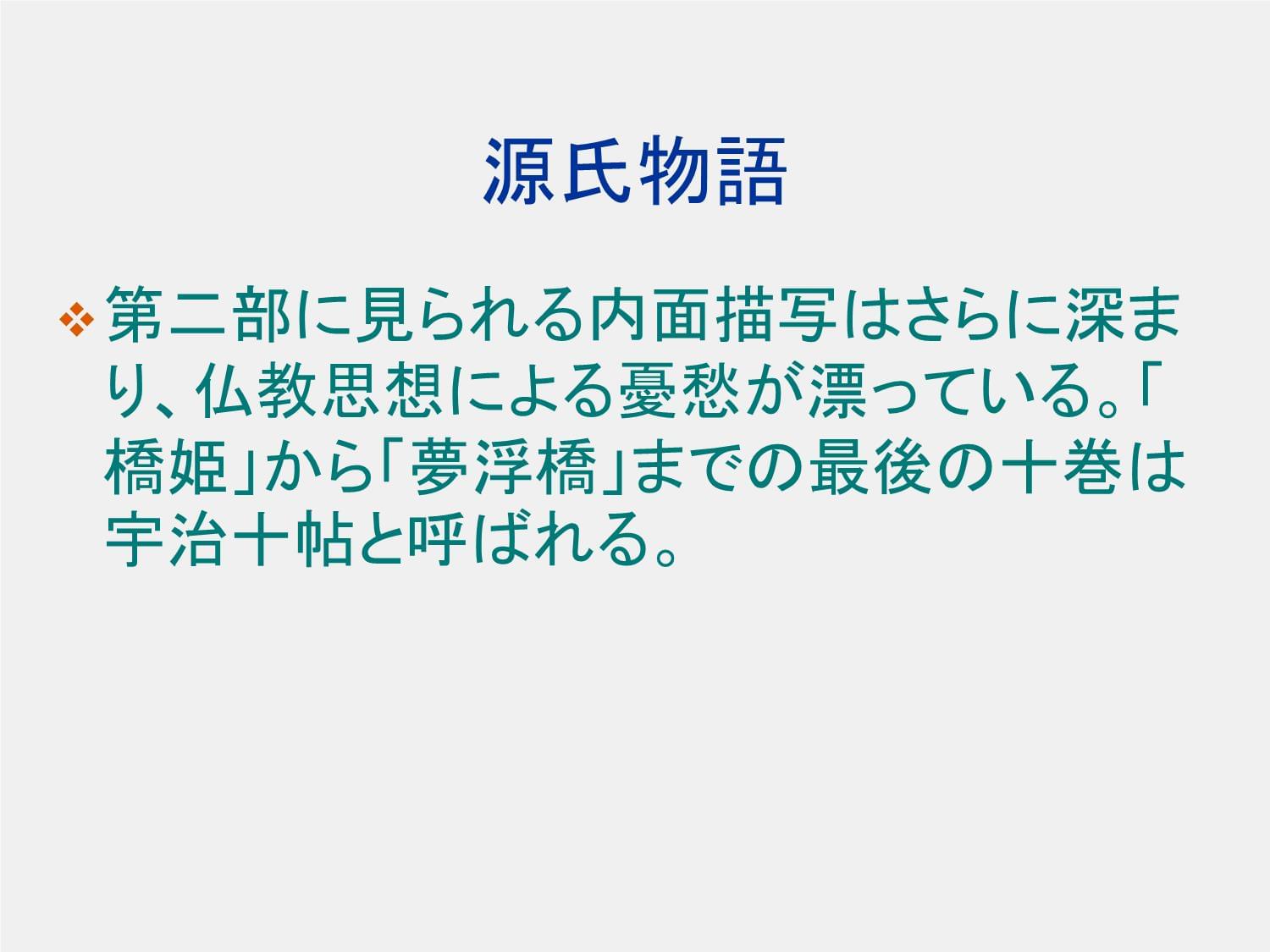


版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
源氏物語華やかな多様な戀愛が中心で、豪華な宮廷生活を背景に、亡き母によく似ている藤壺、その姪で理想の女性紫の上、そのほか夕顔、明石の上などとの交渉が精細に描き分けられた。第二部は「若菜上」から「幻」までの八巻で、華やかな第一部と異なり、悲劇の物語となる。
源氏物語苦悩する光源氏が出家するのを決意し、死を迎えるまでの後半生が描かれている。第三部は「匂宮」から「夢浮橋」までの十三巻で、光源氏の子である薫を中心に、匂宮、宇治の姫君らの満たされぬ戀が描かれ、人間のあり方が追及されている。
源氏物語第二部に見られる內面描寫はさらに深まり、仏教思想による憂愁が漂っている。「橋姫」から「夢浮橋」までの最後の十巻は宇治十帖と呼ばれる。
源氏物語第二部以降、紫式部は一見華やかな貴族社會の背後にあるものを追求し、暗さと深みが加わり、悲愁までも感じさせるが、そこには、作者の深刻な人生批判と真剣な求道精神が見られる。これはほかの物語に見られない優れた點である。源氏物語『源氏物語』に描かれたのは、時間にして帝四代、七十四年、登場人物約四百九十名という膨大な世界である。それにもかかわらず登場人物の性格は見事に描き分けられ、ストーリーの展開上もまったく破綻がない。
源氏物語物語の本質は戀愛小説であるが、実にさまざまな戀愛が書き分けられている、登場人物の心理も深く掘り下げられている。また、自然と人事とが微妙に融合し、全編に「もののあはれ」の情趣を漂わせている。文章は和歌を交え、流麗繊細な分を連ねた代表的な和文體だと言える。源氏物語『源氏物語』は先行諸文學の成果を総合しつつ、それを飛躍的に発展させたもので、日本古典文學の最高傑作と言える。実際、後に王朝文化の象徴として仰がれ、文學のみならず日本文化の前面にわたって甚大の影響を與えている。
源氏物語『源氏物語』の研究書として、本居宣長の『源氏物語玉(たま)の小櫛(おぐし)』、現代語訳として與謝野晶子、谷崎潤一郎、円地文子のものなどが有名である。
源氏物語いづれの御時(おほんどき)にか、女御(にょうご)、更衣あまたさぶらひ給ひけるなかに、いと、やむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めき給ふありけり。はじめより「われは」と、思ひあがり給へる御かたがた、めざましき者におとしめそねみ給ふ。おなじ程、それよりげろうの更衣たちは、まして、安からず。
源氏物語あさゆふの宮づかへにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふつもりにやありけむ、いと、あつしくなりゆき、もの心ぼそげに里がちなるを、いよいよ「あかずあはれなるもの」に思ほして、人の謗(そし)りをも、えはばからせ給はす、世の例(ためし)にもなりぬべき御もてなしなり。源氏物語現代語訳:いつの御代(みよ)のことであったか、女御更衣たちが數多く御所にあがっていられる中に、たいして高貴な身分ではない方で、とりわけ帝の御寵愛を受けている方がいた。
源氏物語宮使えのはじめから、われこそはと自負しておられる方々からは、身の程知らぬ女よと爪はじきして妬まれるし、その人と同じくらい、またそれより一段下った身分の更衣たちにすれば、ましておだやかではない。朝夕の宮仕えにつけても、始終そういう女たちの胸をかき亂し、その度に恨みを負うことの積もり積もったためでもあったろうか。
源氏物語段々病がちになってゆき、なんとなく心細そうにともすれば実家下りの度重なるのを、帝はやるせないまでに不憫なものと思召され、いよいよ愛しさの増さる御様子で、人の非難など一切気にかけようともなさらない。まったく後の世の語り草にもなりそうなお扱いなのであった。(源氏物語冒頭)
源氏物語以上は源氏物語冒頭のところ、つまり第一帖「桐壺」であるが。次は第四十一帖の「幻」の抜粋であるきさいの宮は、內裏に參らせ給ひて、三の宮をぞ、さうざうしき御慰めに、おはしまさせ給ひける。「ははの、のたまひしかば」源氏物語とて、対のお前の紅梅、いと、とりわきて、後見ありき給ふを、あはれと、見たてまつり給ふ。二月になれば、花の木どもの、盛りなるも、まだしきも、こずゑをかしう霞みわたれるに、かの御形見の紅梅に、うぐひすの、はなやかに鳴き出でたれば、たち出でて御覧ず。源氏物語植ゑて見し花のあるじもなき宿に知らず顔にて來ゐるうぐひすと、うそぶきありかせ給ふ。現代語訳:明石の中宮は宮中へお上がりあそばして、三の宮(匂宮)を光源氏のさびしさを慰めるために六條院へお殘しになった。源氏物語「母上が仰せになられたから」(匂宮は紫上にひきとられていた)といって、西の対の御庭先の紅梅を特に大事におもって世話をしておまわりになるのを、光源氏はまことにいじらしく御覧になっていらっしゃる。
源氏物語二月になると、花の咲く木々の、盛りなのも、蕾なのも、一面に梢美しく霞んでいるなかに、紫上の形見の紅梅の木に鶯楽しそうな聲で鳴きたてたので、光源氏は縁に出て御覧になる。源氏物語この梅の木を植えて花を賞でた主(紫の上)もいない宿に、そんなことも知らぬげな顔でやって來て鳴く鶯よ。などと詠じながら、お歩きになられる。源氏物語『源氏物語』のテーマ
作者紫式部は54帖からなる大著でいったい何を表現しようとしたのであろうか。これは各時代の多くの研究者によってさまざまな見解がなされた。江戸時代の國學者の本居宣長が提出した『もののあはれ』がもっとも有力な説である。
源氏物語この説は後代の『源氏物語』の研究に甚大な影響を與え、後の學者に受け継がれ、『源氏物語』を解明する上でのキーワードとなっている。近代になっても、『源氏物語』の本質についての探求が続けられ、いろいろな見解が出されている。代表的な見解はそれぞれ、次のとおりである。
源氏物語1、仏教的立場から栄華の中のむなしさを追求し、『宿世』思想を描いた;2人間性の立場から愛欲のはざまにゆれる人間の弱さや人間相互の心の通い合わぬ寂しさを描いた;3女的な立場から、女性運命への関心や女性の解放と救済を憧憬するものを描いた。このように、研究者の立場や方法によって結論が違う。日記
『土佐日記』蜻蛉日記和泉式部日記紫式部日記更級日記讃岐典侍日記日記日記というものは日本ではもともとあったものであるが、貴族の男性が備忘のために公的あるいは私的行事?儀式、あるいは旅行の出來事をを漢文で記録したもので、実用性が強く文學性に乏しい。
日記紀貫之は日記を実用から解放して、人間の內面を表現するための手段とする道を開いた、貫之は漢文を用いずかな文字で、そして女性の立場に立って『土佐日記』を書いたのである。その後、女性の手になる日記文學が盛んに行われるようになった。日記『土佐日記』に続いて、『蜻蛉日記』、『和泉式部日記』、『紫式部日記』、『更級日記』などが書き継がれていった。平安後期になると、また『成尋阿闍梨母集(じょうじんあじゃりのははのしゅう)』と『讃岐典侍(さぬきのすけの)日記』が現れた。いずれも中流貴族の女性の手になり、日々の記録ではなく、後日の回想により、自分の人生の意味を問うものである。
日記これは彼女たちが不安定な貴族社會の中で現実の矛盾の集中する立場に置かれて、人生の不安を自覚せざるを得なかったことも大きな理由である。漢文に縛られていた男たちの中から自照文學と呼べるものが生まれたのは、かな文の果たした役割が黙視できない。『土佐日記』
『土佐日記』は紀貫之が土佐守の任期を終えて帰京したときの旅日記として書かれた。その冒頭には「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」と書かれ、男が漢文で日記を書くという習慣を打破し、女の手でかなを使って日記を書いてみようと宣言した。
『土佐日記』日記で任期でわが子を失ったことの悲しみや船旅のこと、海賊襲來の恐れ、途中の珍しい風景、帰京したときの喜びなど感情的に述べられている。人間を心の內側から記述する道を開いている。文章は簡潔で文體が平淡軽妙であり、余情に富んでいる。『土佐日記』男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなりそれの年の十二月の二十日あまり一日の日の戌の時に、門出す。そのよし、いささかに物に書きつく。……『土佐日記』いけめいてくぼまり、みつづけるところあり。ほとりにまつもありき。いつとせむとせのうちに、千とせやすぎにけん。かたへはなくにけり。いまおひたるぞまじれる。おほかたのみなあれにたれば、「あはれ」とぞひとびといふ。
『土佐日記』おもひいでぬことなく、おもひこひしきがうちに、このいへにてうまれしをんなごのもろともにかへらねば、いかがはかなしき。ふなびともみな、こたかりてののしる。かかるうちに、なほかなしきにたへずして、ひそかにこころしれるひとといへりけるうた。『土佐日記』むまれしもかへらぬものをわがやどにこまつのあるをみるがかなしきとぞいへる。なほあかずやあらん、またかくなんみしひとのまつのちとせにみましかばとほくかなしきわかれせましや『土佐日記』わすれがたく、くちをしきことおほかれど、えつくさず、とまれかうまれ、とくやりてん。(土佐日記冒頭と終わりの部分)『土佐日記』[現代語訳]男が書くという日記というものを、女も書いて見ようというので書くのである。ある年の十二月二十一日の午後八時ごろに出発する。その旅のいきさつをほんの少し物に書き付ける。……池みたいにくぼんで、水のたまっている所がある。そばに松もあった。
『土佐日記』留守にしていた五年か六年の間に、千年も立ってしまったのだろうか、半分はなくなってしまっていた。新しく生えたのが混じっている。だいたいがすっかり荒れてしまっているので、「まあひどい」と人々は言う。
『土佐日記』思い出さぬこととてなく、その悲しい思いの內にも、この家で生まれた女の子が、任地で死んで、どんなに悲しいことか。同船の人も、みな子供が寄ってたかって騒いでいる。こうした騒ぎの中で、いっそう悲しさに堪えかねて、そっと気持ちのわかっている人とが読みかわした歌は『土佐日記』この家で生まれた子さえ土佐で死んで帰って來ないのに、留守中の我が家に小松が新しく生え育っているのを見るのが悲しい。といったことだ。それでもまだ言い足りないのか、またこんなふうに。
『土佐日記』かつて生きていた子が、千年の齢を持つ松のように長く生きていたとしたら、遠い土佐であのような悲しい永遠の別れをしただろうか。そんなことはなかったろうに。忘れられない、心殘りなことがたくさんあるけれども、とても書き盡くせない。何はともあれ、早く破ってしまおう。
蜻蛉日記『蜻蛉日記』は974年に成立し、上?中?下の全三巻からなり、作者が藤原道綱母である。作者は藤原倫寧(ともやす)の娘で、二十歳のころ藤原兼家と結婚し、翌年道綱(みちつな)を生んだ。才媛であり美人でもある。この日記は女性の手による最初のかな日記である。
蜻蛉日記作者自身の満たされない結婚生活の苦悩と煩悶を、二十一年にわたって回想的につづった作品である。権門の妻妾の一人となった道綱母が、夫の専心な愛を求めたが、夫には愛人ができてから、數十年にわたる嫉妬と寂寥の生活が続いた。
蜻蛉日記結局、彼女は夫への愛をあきらめ、子である道綱をひたむきに愛することで慰めを見出そうとしてゆく。『蜻蛉日記』には作者のそのようなひたむきな心情が赤裸々につづられている。自照性を備えた女流日記文學の先駆として、『源氏物語』をはじめ後世の文學に大きな影響を與えている。
蜻蛉日記かくありし時すぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで、世にふる人ありけり。かたちとても人にも似ず、こころだましひもあるにもあらで、かうものの要にあらであるもことはりと思ひつつ、ただふしをきあかしくらすままに、……
(蜻蛉日記冒頭)
蜻蛉日記[現代語訳]
若かった日も過ぎ去って、世の中はたいそう頼りなく、どちらとも決めかねて結婚生活を送っている人がいた。容貌も人並み以下で、思慮深さもろくになく、このように(夫から)必要とされずに過ごしているのも、當然だと思いながら、ただ寢たり起きたり毎日を過ごしているうちに、……
和泉式部日記1004年ころできた日記である。和泉式部と冷泉院の皇子敦道親王との十ヶ月ばかりの戀愛の経緯を記したもので、身分の違う二人のやるせない戀愛が百四十七首の贈答歌を中心に語られる。和泉式部日記日記は敦道の求愛から始まり、二人の愛の世界にある熱情的情趣を率直に記した。作者は第三人稱で客観的に敘述し、歌物語的性格を持つ。
紫式部日記紫式部が1008年から1010年までの華やか宮廷生活を記したものである。日記には當時の貴族社會の儀式や行事、自分の感想、當時の女流作家清少納言?和泉式部に対する批評などを書いた。
紫式部日記中宮の女房として書いた日記なので、公的な性格を持っているが、華やかな宮中生活に馴染めない作者の哀れな気分が感ぜられる。日記においては清少納言や和泉式部に対する批評は痛烈で、清少納言とは対照的な作者の性格などがうかがえる。
更級日記1060年に成立し、作者が菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)である。菅原孝標女は物語に憧れてそだったが、のちに親しい人々の死別、宮仕え、結婚生活を経て、夫と死別し、孤獨に老いてゆく。作者は厳しい現実に直面して、次第に幻滅を味わいついに信仰に生きようとするまでの魂の遍歴がある。
更級日記晩年の寂寥の中で、過去四十年(13歳から52歳)にわたる生涯を回想して、平明な筆致で自序伝的な日記を書いた。全體は暗い感傷的な情けが漂っているが作者は夢想的な性格を持っているので、日記の中で夢についての描寫が多く、ロマン性が満ちている。現実の中に、夢と幻とがしきりに交錯しているのが、この作品の特色である。
讃岐典侍日記これは平安末期の作品で、1108年ころ書かれたと推測され、作者は藤原長子とされる。堀河天皇の崩御と鳥羽天皇の即位とを記した歴史物語的な日記である。藤原長子は堀河天皇に使えた女房であったが、後は鳥羽天皇に仕えたことがある。
讃岐典侍日記日記は上下二巻に分かれ、上巻は堀河天皇の病気になることから逝去までの看病記録で、下巻は鳥羽天皇に仕え、先帝を偲ぶことを記している。文章は冗漫ではあるが宮中の様子についての記事が詳しく、作者の堀河天皇に対する情愛もよく滲み出ている。
二、隨筆隨筆は形式にとらわれず、さまざまな事象を心の赴くままに書きとめたものである。十世紀の末になると日本の宮廷文化が大きく発達し、才子才女を輩出し、人々の感覚は繊細の極地に洗練されたが、そういう宮廷文化を背景に、自然や人事について自由な筆致で書いた作品が現れた。『枕草子』がそれである。枕草子一條天皇の中宮定子に仕えた清少納言が書いたものである。三巻から成る。三百編余の長短さまざまな文章を集めたもので、宮廷生活の回想?見聞または自然?人事に関する隨想などをもとにして、日記に類するものも含んでいる。普通は物盡し(類聚)の章段、隨想的な章段と日記的な章段に分けられている。
枕草子物盡しの章段では、「木の花は」、「鳥は」のように、いわば美的連想を語るものと、「うつくしきもの」「すさまじきもの」のように、共通の心情語によって、一括できるものを列挙して、作者の美的感覚を示したものとがある。枕草子隨想的な章段では、「春はあけぼの」、「月のいと明かきに」というような見聞したものをもとにするものである。この隨想的な章段には自然を主とするものと、人事を主とするものとが含まれ、獨自の視覚と新鮮な著想をもっている。枕草子日記的な章段は「宮にはじめてまゐりたるころ」「雪のいと高う降りたるを」のように、宮廷貴族や中宮定子に対する褒賞や筆者の自慢話などの內容である。特に中宮定子を中心とした宮廷の様子が明るく、生き生きと寫し出されている。その鋭い感受性と歯切れのよい文章表現はほかに類例がない。
枕草子『枕草子』は『源氏物語』とともに平安王朝の女流文學の雙璧といわれている。『源氏物語』が「もののあはれ」の情趣を中心としているのに対して、『枕草子』は「をかし」という知的態度で作られたと言えよう。枕草子「枕草子」という題名は中宮定子に兄の藤原伊周(これちか)から紙が獻上されたときに、清少納言が「枕にこそ侍らめ」といって賜ったのに基づく。だいたい「枕に置くメモ」という意味である。枕草子春はあけぼの、やうやうしろくなり行く、山ぎはすこしあかりて、むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。夏は夜。月のころはさらなり。闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くものをかし。雨など降るもをかし。枕
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 媒體資源協作合同(2篇)
- 地磚改造租房合同范本
- 2025至2030年中國印刷夾棍市場現狀分析及前景預測報告
- 2025至2030年中國單層熱壓機市場現狀分析及前景預測報告
- 2025至2030年中國匝間絕緣測試儀數據監測研究報告
- 2025至2030年中國動態可調光衰減器行業投資前景及策略咨詢報告
- 2025至2030年中國加熱溶劑型反光標線涂料市場分析及競爭策略研究報告
- 2025至2030年中國凹凸海綿行業發展研究報告
- 2025至2030年中國冶煉電爐濕式除塵器行業發展研究報告
- 2025至2030年中國六角扁鏟市場分析及競爭策略研究報告001
- 火鍋店創業計劃書:營銷策略
- 交通大數據分析-深度研究
- 基礎護理學試題及標準答案
- DB11-T 1754-2024 老年人能力綜合評估規范
- 招聘團隊管理
- 【課件】用坐標描述簡單幾何圖形+課件人教版七年級數學下冊
- 電商運營崗位聘用合同樣本
- 2023年浙江省杭州市上城區中考數學一模試卷
- 租賃鉆桿合同范例
- 消毒管理辦法
- 湖北省黃岡市部分學校2024-2025學年七年級上學期期中地理試卷(含答案)

評論
0/150
提交評論